1976年の夏はアメリカ独立200年祭の夏で全米各地で様々な催しが予定されていて、こころもち国民全体がうきうきしているような明るさが感じられた。
休み前になると、大学のキャンパスの掲示板にはサマー・ジョブを含めた色々なイベント情報が貼られ、学生はそれを見ながら各自の計画をたてる。大まかには、帰省、旅行、アルバイト、勉強の4派に分かれるが3ヵ月を越える休暇を一種類で過ごす学生はすくなく、ほとんどが家族のことや自分の懐具合を考えて、2つないし3つを組み合わせて長い夏休みをすごすのであった。
学生相手の格安旅行ではあるが、日程をみると心憎いまでの配慮がうかがわれて、誘い込まれそうになる。主宰者は業者ではなく、ヴィエナ大学のメンバーによって設立された「ヨーロッパ・イクスポーレーション」という非営利団体である。イリノイ大学につくられた「ヨーロッパ・ハウス」と提携して北米の大学生をヨーロッパに送り込んでいる。設立以来既に16年の実績もあり宣伝文句にも自信のほどがうかがえた。
その年は17回目のプログラムで、北米から1400名以上の大学生が参加した。申込みには3人からの紹介状と、信用ある人物からの推薦状がいるという慎重さで、それでかえって安心させられた。私はすぐに会社に手紙をかいて、国内に残しておいた預金から全額を引き出して送ってくれるように頼み、推薦状をニックに頼んだ。費用は1人1300ドルで、これにはニューヨーク‐ロンドン間の往復飛行機代と、ヨーロッパでの交通、宿泊、3度の食事、入場料の総てが含まれている。当時の為替ではおよそ40万円であるが、今で言えば15万円そこそこの金額である。セントルイス‐ニューヨーク間の旅費と写真関係費、その他みやげ代を含めて、2人で総計150万円くらいの旅になったであろうか。それでも安いし、そもそも8週間で13ヶ国を巡る旅など二度と機会はないであろうという確信があった。
バス1台分の人数からなるグループに分かれ、5月下旬よりさみだれ式に出発していく。欧州大陸出発点カレーから終点アムステルダムまでは、同じ運転手とグループ・リーダーとともにバス1台で48日を共に過ごすのである。私たちのバスの運転手は妻子ある粋なパリジェンで、後に2人の女の子が恋におちいることになった。グループ・リーダーはウィーン大学の哲学専攻の大学院生で、毎年夏休みのアルバイトとしてこのツアーを楽しみにしているのだそうだ。ちょび髭をはやし、難しそうな顔をしてドイツ語なまりの英語を話す男だったが、笑顔がかわいくてヒューモアのセンスを身につけた好青年であった。訪ねる土地にはそれぞれ地元出身の、大学で美術史を専攻した職業ガイドが待っていた。今までの活動実績を通じて、グループ・リーダーとはお互いに知り合いの間柄である。
私のグループにはカップルが3組参加していた。カナダから参加した学生夫婦、ミシシッピーからきた独身カップル、そして私たちである。このなかでミシシッピー組はいつもバスの最後部に陣取って仲間とはすこし距離を置いていた。アラバマから来たという赤毛の小柄な女の子と、ニューヨークからきた背が高くてモデルでもできそうなグラマー女性の2人は、席を争って運転手の近くに座るようにした。
私たちはバスの中ほどで、親しくなったテキサスのダイアンと、オクラホマ大学のクラスメートだというキャシーとロウアンの近くに座ることが多かった。この南部3人組は性格がさっぱりしたいい子で、日本のことに興味があるらしくさかんに私や妻にゆっくりした英語で話しかけてくるのだった。おそらく彼女らにとって日本人を見るのは初めてだったのではないか。グループのほとんどが女性で、男はカップルの3人を除くと、トロントとオハイオから来た学生2人だけで、バスのなかはいつも甲高い声でにぎやかだった。
日程要約
日程はつぎのとおりで、欧州13ヶ国を回る。カッコの中はその時買った土産である。貨幣の使いのこしや、入場券、パンフレット類は2冊のスクラップブックに貼り付けた。今それを見ながら思い出している。為替レートや人口など統計数字は当時のものである。欧州通貨がすべてユーローに変わった今、保存してある貨幣は歴史的価値を帯びて見える。1日目‐4日目 パリ(手鏡、足つき皿、ネクタイ、人形)
5日目 パリからヴェルサーユ、ロワール・ヴァレー・シュヌーソーへ
7日目 ハイデルベルク
8日目 ハイデルベルグからスイスのルーツェルンへ。エントルバッハ泊
10日目 山登り(エーデルワイスの押し花)ザース・アルマゲル泊
11日目 シンプロン峠を越えてヴェネチアへ
12日目 ヴェネチア
13日目 フローレンスへ
14日‐15日目 フローレンス(彩色盆)
16日‐17日目 ローマ(人形)
18日目 ナポリ、ポンペイを経てソレントへ(カメオ)
19日目 カプリ島
20日目 イタリア南部ブリンディシからギリシャにむけて一泊の船旅
21日目 デルファイ
22日目 デルファイからアテネへ
23日目 アテネ(人形、テープ)
24日目 アテネからヒドラ島へ
25日目 ヒドラ島(ドルフィン指輪、ダイヤとルビーの指輪)
26日目 アテネからテサロニキへ
27日目 テサロニキからユーゴスラヴィア、ベオグラードへ
28日目 ベオグラード(織物ベルト、ピンクッション、人形)
29日目 ベオグラードからリュブリャーナへ
30日目 ユーゴスラヴィアからオーストリアへ。ペンク泊
31日目 グロスグロックナーを経てザルツブルグへ
32日目 ザルツブルグ
33日‐35日目 ヴィエナ(ブローチ、ペイストリーの本、人形)
36日目 ヴィエナからチェコスロヴァキア、プラハへ
37日目 プラハ(人形、テープ)
38日目 テレジンナチ強制収容所を見てベルリンへ
39日‐41日目 東西ベルリン(人形、ゾーリンゲンのナイフと髪バサミ)
42日目 ベルリンからコペンハーゲンへ
45日目 コペンハーゲンからスエーデン、ヘルシンボリへ
46日目 ヘルシンボリからアムステルダムへ
47日目 アムステルダム(木靴、人形、テープ)
48日目 アムステルダムよりロンドンへ
4日間 ロンドン
ケネディ空港に集合した一行は団体ツアー用のディスカウント便でロンドンに向かう。6日間のロンドン観光が始まった。
帰路もロンドンに4泊した後ニューヨークへ帰った。イギリスについては往復10日間の記録である。
1.イギリス
| 美しいカントリーサイド ひ弱そうなイギリス青年 |
というメモ書きが残っていた。おそらくセントルイスで見た初めてのアメリカの風景と男性の印象を、イギリスのそれと比較したのであろう。
ロンドン
ロンドンは人口770万人の大都会である。北緯およそ52度に位置し、カムチャッカ半島の南端と同じくらい北にある。夏の平均気温は17度と日によってはセーターがいるが、冬は暖流のために東京とさほど違わない。この地の印象については自分史の「ロンドン時代」の他、欧州紀行の「イングランドの旅」でも書くこととして、今回の旅を急ぐ。

ロンドンには初めてみる物が多かった。2階建ての赤いバス、木製肘掛けのある地下鉄電車、内部が高くて広い黒のタクシーなど。街を歩く人の中にはインド人やギリシャ人、イタリア人などが目についた。これらの風景はセントルイスにはなかったものである。
 テムズ川に架かるタワーブリッジはゴシック風の尖塔が中世の城を思わせる。橋というより一連の建物のように威張ってみえる。その橋本にあるのがロンドン塔で、多くの政治犯の牢獄となった陰湿な建物である。今は青々としている中庭では、かってヘンリー8世の2人の妻も含めて多数の男女の首が斧の餌食となった。イギリス王室の宝石やダイヤモンドをちりばめた王冠も、古色が勝って華やかを感じさせなかった。この王冠こそが幾多の命を陰惨なやりかたでもてあそんだ張本人であったのだ。
テムズ川に架かるタワーブリッジはゴシック風の尖塔が中世の城を思わせる。橋というより一連の建物のように威張ってみえる。その橋本にあるのがロンドン塔で、多くの政治犯の牢獄となった陰湿な建物である。今は青々としている中庭では、かってヘンリー8世の2人の妻も含めて多数の男女の首が斧の餌食となった。イギリス王室の宝石やダイヤモンドをちりばめた王冠も、古色が勝って華やかを感じさせなかった。この王冠こそが幾多の命を陰惨なやりかたでもてあそんだ張本人であったのだ。 時計台の元祖ともいえるビッグベンが国会議事堂から見下ろしている。その隣はゴシック建築の代表格、ウェストミンスター寺院である。ともにテムズ川に面していて、対岸から見る姿がよい。
時計台の元祖ともいえるビッグベンが国会議事堂から見下ろしている。その隣はゴシック建築の代表格、ウェストミンスター寺院である。ともにテムズ川に面していて、対岸から見る姿がよい。マダム・タッソーに1人の日本人がいた。袴姿・羽織・草履姿で椅子に腰掛ける吉田茂は、並み居る蝋人形の中でも一段と背が低かった。ロンドン時代に2度目に訪れた時は、チョンマゲに裸姿の大鵬が加わっていたと記憶している。西洋人は異様な姿でしか日本人を認識できないらしい。かって、映画やミュジカルで、着物を左右逆に重ね、花魁のようなはでな櫛をかざした日本人女性を見せられたことがある。日本について西洋の認識はその程度であることが多い。

ナポレオンは小人で、頭の毛は薄く智恵だけは働くが貫禄のない男に見えた。ビートルズ、バロステロス、オードリー・ヘップバーンなど多くの有名人がいたが今ひとつ拍手したくなるでき栄えではない。一番似ていたといえば椅子に腰掛け振り向いていたピカソだろうか。
「恐怖の間」がマダム・タッソー蝋人形館のはじまりである。もともとパリにいたタッソーがフランス革命の犠牲者のデスマスクを作ったことから始まったといわれている。ギロチンの刃と共に並べられたマリー・アントワネットの首は哀れというよりグロテスクであった。デスマスクを作ること自体がそもそも悪趣味ではある。
 大英博物館は欲深い。エジプトのミイラ、アッシリア宮殿の翼のある雄牛など、自国のものより外国からぶん取ってきたもののほうが圧倒的に多い。アクロポリスの丘に立つパンテオンから大理石のフリーズを削り取ってきたし、ナポレオンのエジプト遠征軍が発見したロゼッタ石を横取りした。現在のイギリス人からは想像もつかない強引なやり方は、植民地時代の傲慢さとしか思えない。
大英博物館は欲深い。エジプトのミイラ、アッシリア宮殿の翼のある雄牛など、自国のものより外国からぶん取ってきたもののほうが圧倒的に多い。アクロポリスの丘に立つパンテオンから大理石のフリーズを削り取ってきたし、ナポレオンのエジプト遠征軍が発見したロゼッタ石を横取りした。現在のイギリス人からは想像もつかない強引なやり方は、植民地時代の傲慢さとしか思えない。セイント・ポール大聖堂は1710年に建った、ローマのサン・ピエトロ、フローレンスのドゥオモに次ぐ世界で3番目に大きい聖堂である。私が赴任していた頃、バブルに乗った日系資本家がセント・ポール大聖堂の近くにそれを凌ぐ高層ビルを建てる計画があって、それを知ったチャールズ皇太子がいたく反対したという話しがあった。
 バッキンガム宮殿はエリザベス女王の居所で、毎日衛兵の交替の儀式が人を楽しませている。ここに限らずロンドンにはいたるところで、目が隠れるほどに深く帽子をかぶり、ただひたすらに前を見据えて直立不動で立っている門番を見かける。一見何もしなくて楽そうに見えるが、動かないことが仕事となれば、それは動くよりも結構きついのではないかと思われた。
バッキンガム宮殿はエリザベス女王の居所で、毎日衛兵の交替の儀式が人を楽しませている。ここに限らずロンドンにはいたるところで、目が隠れるほどに深く帽子をかぶり、ただひたすらに前を見据えて直立不動で立っている門番を見かける。一見何もしなくて楽そうに見えるが、動かないことが仕事となれば、それは動くよりも結構きついのではないかと思われた。ロンドン郊外

 ロンドン郊外にも見るべき物が多い。日をわけてストーンヘンジ、ストウク・ポージス・ペリッシュ教会、ソールズベリー大聖堂を見てまわった。イギリスの第一印象として「美しいカントリーサイド」と記したのはこの日のロンドン郊外の風景だったと思われる。日本の田園地帯を走る新幹線の車窓の景色は、土の色と高く伸びた雑草と広告看板が障害となって、八割り方美しく仕上がった絵を完成させようとしない。イギリスだけでなくヨーロッパの農村は緑一色の絨毯で覆われていて邪魔をするものがない。それに加えて、国土が常にゆったりと波打っているのも、車窓からの風景に立体感を加味して好ましい。
ロンドン郊外にも見るべき物が多い。日をわけてストーンヘンジ、ストウク・ポージス・ペリッシュ教会、ソールズベリー大聖堂を見てまわった。イギリスの第一印象として「美しいカントリーサイド」と記したのはこの日のロンドン郊外の風景だったと思われる。日本の田園地帯を走る新幹線の車窓の景色は、土の色と高く伸びた雑草と広告看板が障害となって、八割り方美しく仕上がった絵を完成させようとしない。イギリスだけでなくヨーロッパの農村は緑一色の絨毯で覆われていて邪魔をするものがない。それに加えて、国土が常にゆったりと波打っているのも、車窓からの風景に立体感を加味して好ましい。  巨石遺構ストーンヘンジはイギリス南部のソールズベリーにある。紀元前2800年頃に最初の建設が始まったと考えられている。敷地は円形の土手で囲まれ、その外周に堀が巡らされていて入り口にはヒルストーンが立てられていた。紀元前2千年頃になると200km以上離れた山から、1つ4トンほどのブルー・ストーンを何10個も運んできて敷地内に並べた。その後苦労して運び込んだブルーストーンを敷地の外へ運び出して別の巨石を搬入し同心円状に組み上げたのである。
巨石遺構ストーンヘンジはイギリス南部のソールズベリーにある。紀元前2800年頃に最初の建設が始まったと考えられている。敷地は円形の土手で囲まれ、その外周に堀が巡らされていて入り口にはヒルストーンが立てられていた。紀元前2千年頃になると200km以上離れた山から、1つ4トンほどのブルー・ストーンを何10個も運んできて敷地内に並べた。その後苦労して運び込んだブルーストーンを敷地の外へ運び出して別の巨石を搬入し同心円状に組み上げたのである。円形の敷地は直径が114mあり、そのなかに4重円の巨石の列がある。巨石には文字は刻まれておらず周辺からも手がかりになるようなものは出土していないためストーンヘンジが何のための施設なのかよくわかっていない。太陽崇拝にからんだ宗教施設との見方や古代の天文台であろうという説もあるが謎は今も解けていない。
その後、それ以上に不可解なことがこの近くに起こった。麦畑の真中で、ある日突然円形脱毛症のように麦がなぎ倒されていたのだ。丁寧にもその円に至る滑走路のような直線の跡まで残していた。24時間カメラを設置しても犯人らしき像を捕らえることができなかった。ユーホー説や、ストーンヘンジの亡霊説や、竜巻説など、様々な科学的分析が試みられたが結論に至らず、結局その円形は「ミステリー・サークル」のままに据え置かれた。
 他の1日はシェイクスピアに会いに行くことになった。場所はロンドンから北西に150km行ったストラト・アポン・エイボンである。途中90km行ったところに大学の町オックスフォードがあるが、カレッジの建物が並ぶだけであまり面白そうでもないので素通りすることになった。
他の1日はシェイクスピアに会いに行くことになった。場所はロンドンから北西に150km行ったストラト・アポン・エイボンである。途中90km行ったところに大学の町オックスフォードがあるが、カレッジの建物が並ぶだけであまり面白そうでもないので素通りすることになった。 ストラト・アポン・エイボンは、元々はエイボン川の中流にできた市場町である。ハイ・ストリートとよばれる商店街は木の骨組が露出したチューダー調の建物が並び、16世紀の町に迷い込んだ気分にさせる。その一角にあるハーヴァード・ハウスはボストンにあるハーヴァード大学の創設者ジョン・ハーヴァードの母親、キャサリン・ロジャーズの生家である。板屋根と、白壁に浮き出るような木枠が美しい。
ストラト・アポン・エイボンは、元々はエイボン川の中流にできた市場町である。ハイ・ストリートとよばれる商店街は木の骨組が露出したチューダー調の建物が並び、16世紀の町に迷い込んだ気分にさせる。その一角にあるハーヴァード・ハウスはボストンにあるハーヴァード大学の創設者ジョン・ハーヴァードの母親、キャサリン・ロジャーズの生家である。板屋根と、白壁に浮き出るような木枠が美しい。 シェイクスピアの生家と彼の妻、アン・ハサウェイの実家をみた。共に、草花を咲き育つにまかせたさりげない庭をかまえ、自然の趣をたたえている。イングリッシュ・ガーデンの原型はこのようなものかと思われた。アン・ハサウェイの実家はコテッジといわれるように農家風の小屋ともいえる建物で、とくに丸みをおびた茅葺きの屋根は絵本にでてくるかわいらしい子豚の家を連想させる。日本の茅葺きの屋根は軒に向かって上に反らすが、イギリスの農家は下に反っているのもおもしろい。
シェイクスピアの生家と彼の妻、アン・ハサウェイの実家をみた。共に、草花を咲き育つにまかせたさりげない庭をかまえ、自然の趣をたたえている。イングリッシュ・ガーデンの原型はこのようなものかと思われた。アン・ハサウェイの実家はコテッジといわれるように農家風の小屋ともいえる建物で、とくに丸みをおびた茅葺きの屋根は絵本にでてくるかわいらしい子豚の家を連想させる。日本の茅葺きの屋根は軒に向かって上に反らすが、イギリスの農家は下に反っているのもおもしろい。
 ロンドン近郊にはウィンザー・キャースルやハンプトン・コートがある。ウィンザー・キャースルの入口で、恰幅のよいヴィクトリア女王おばさんに出会ったほかは、あまり記憶にない。私はいつもムーヴィーと写真に忙しく、グループからは外れてガイドの説明を聞くことが少なかったのだが、この時は珍しく群れに入っていた。ガイドが歩道の横の溝を指差して、「当時はここに糞尿も一緒に流れていた」と真顔で説明していた。妙なものでなんとなく鼻をきかせると、なつかしい肥えたごの臭いが漂ってくる気がしてきた。
ロンドン近郊にはウィンザー・キャースルやハンプトン・コートがある。ウィンザー・キャースルの入口で、恰幅のよいヴィクトリア女王おばさんに出会ったほかは、あまり記憶にない。私はいつもムーヴィーと写真に忙しく、グループからは外れてガイドの説明を聞くことが少なかったのだが、この時は珍しく群れに入っていた。ガイドが歩道の横の溝を指差して、「当時はここに糞尿も一緒に流れていた」と真顔で説明していた。妙なものでなんとなく鼻をきかせると、なつかしい肥えたごの臭いが漂ってくる気がしてきた。 ロンドンの風景は多くの映画を思い出させる。「メリー・ポピンズ」は、まだ高層ビルがなかった時代のロンドンを空から俯瞰するのによい。特に、街を歩くと必ず視野に入ってくる竹の子のような暖炉の煙突を、クローズ・アップで見せてくれる。
ロンドンの風景は多くの映画を思い出させる。「メリー・ポピンズ」は、まだ高層ビルがなかった時代のロンドンを空から俯瞰するのによい。特に、街を歩くと必ず視野に入ってくる竹の子のような暖炉の煙突を、クローズ・アップで見せてくれる。 「ウォータルー・ブリッジ」はそのままの名の悲しい名画がある。邦題名は「哀愁」と訳され、「君の名は」の原点となった。第一次世界大戦下、空襲警報が鳴りわたるウォータールー橋で出会った将校クローニンとバレエの踊り子マイラ(ヴィヴィアン・リー)は互いに惹かれ合い、レストランで別れのワルツ(蛍の光)が演奏される中ローソクの灯が消えるにあわせて2人は唇を重ねる。結婚の約束をしてフランスの戦場に赴いたクローニンの帰りを待つマイラに届いたのは彼の死をしらせる新聞公告だった。生活のために身を落とし、ウォータルー駅で帰還兵に媚を売っていた彼女の前に嬉々として手を振るクローニンが現れる。
「ウォータルー・ブリッジ」はそのままの名の悲しい名画がある。邦題名は「哀愁」と訳され、「君の名は」の原点となった。第一次世界大戦下、空襲警報が鳴りわたるウォータールー橋で出会った将校クローニンとバレエの踊り子マイラ(ヴィヴィアン・リー)は互いに惹かれ合い、レストランで別れのワルツ(蛍の光)が演奏される中ローソクの灯が消えるにあわせて2人は唇を重ねる。結婚の約束をしてフランスの戦場に赴いたクローニンの帰りを待つマイラに届いたのは彼の死をしらせる新聞公告だった。生活のために身を落とし、ウォータルー駅で帰還兵に媚を売っていた彼女の前に嬉々として手を振るクローニンが現れる。「どうして今帰ってくるって知ってたの?」
彼をだましきれないと知った彼女は思い出のウォータルー・ブリッジで、赤十字のマークをつけた軍医車両の列に身を投げた。
それから・・・・髪に白いものが混じるようになったクローニンはウォータルー・ブリッジの歩道にたち、彼女の言葉を回想する。
| I loved you. I never loved anyone else. I never shall. |
| あなたを愛していました。他の人を愛したことは一度もありません。これからも決して。 |
セントポール寺院のドームが霧にかすみ、テムズの上を別れのワルツが流れていた。
トップへ
2.フランス
ラムズゲイトからホーバークラフトで大西洋をわたり、フランスのカレーに着く。パリからバス一台と、ヴィエナからちょび髭のグループリーダーが出迎えにきていた。
| 花の多い国。オニオン・スープ、エスカルゴ、ワイン |
と食べ物中心である。今ひとつ追加するとすれば、「英語はダメ」と書くであろう。
パリ
第1日目はホテルにチェックインして、47日間欧州大陸12ヶ国の旅のオリエンテーションを受ける。
2日目の午前はルーブル、ノートルダム、ソルボンヌなどの歴史散歩で、午後はエリーゼ宮殿、エッフェル塔、シャンゼリゼなどの近代のパリを見て歩いた。エッフェル塔の前で、バスを降り立つやいやしげな男が写真を胸にかかえるようにして私に近寄ってきた。「いい写真があるよ」と見本をチラッと見せて小声でささやく。アメリカ人を差し置いてまず私に寄ってきたのが気にいらなかった。
 シャンゼリゼは広い。広くて華麗な通りである。遠くに凱旋門が立ちはだかって通りがそこに吸込まれていくように見える。そこからまた12本の大通りが放射線状に出ているのだ。遠近法をみごとに取り入れた市街設計の傑作といってよい。
シャンゼリゼは広い。広くて華麗な通りである。遠くに凱旋門が立ちはだかって通りがそこに吸込まれていくように見える。そこからまた12本の大通りが放射線状に出ているのだ。遠近法をみごとに取り入れた市街設計の傑作といってよい。ノートルダム寺院で1804年、ナポレオンの戴冠式が行われた。その巨大な絵がルーブル美術館にあり、ホールの後ろまで下がらないと全体が見渡せない。同じ絵がたしかヴェルサイユ宮殿にもあったような気がする。
 その昔、ノートルダム寺院の前の広場で石に打たれるジプシー女を、寺院に住み込むせむしの鐘突き男が救い出した。彼はかわって大衆のさらしものになる。いつしかモーリン・オハラ扮するその女を愛するようになるが、自分の宿命になすすべをもたない哀れなせむし男は、ただ、ひたすら鐘を突きつづけるしかなかった。あの鐘の音はカジモドのやるせない愛の告白だったのである。
その昔、ノートルダム寺院の前の広場で石に打たれるジプシー女を、寺院に住み込むせむしの鐘突き男が救い出した。彼はかわって大衆のさらしものになる。いつしかモーリン・オハラ扮するその女を愛するようになるが、自分の宿命になすすべをもたない哀れなせむし男は、ただ、ひたすら鐘を突きつづけるしかなかった。あの鐘の音はカジモドのやるせない愛の告白だったのである。私は同性の男として、彼の純情に涙した。報われるべくもないカジモドの恋心を、エンパイア・ステート・ビルのラジオ塔にかじりつきながら、手のひらに抱えた乙女を、目を細めていつくしむキング・コングの心にだぶらせていた。
夜はビストロでキャンドルの灯のもと、フレンチ・オニオン・スープとワインを楽しんだ後、バトー・ムシュでセーヌ川を遊覧する。光の洪水を浴びたパリの最も美しい時である。

 3日目の午前は自由に過ごし、午後、ルーブル美術館に入る。まず最初にヘレニズム芸術の傑作、サモトラケの勝利の女神ニケとミロのヴィーナスが出迎える。ニケには顔がないのが残念であるが、ヴィーナスの端正な顔は見ていて飽きない。さらに飽きないのは理想的な形の乳房で、誰もいなければ触れたくなる衝動にかられる。広いホールが続き、学生時代の美術教科書でみた絵がすべてある。展示品の総数は20万を超え、目録品数は40万という膨大なコレクションである。ナポレオンは戦利品として獲ってきたあとも、敗戦国に美術品を要求し続けた。
3日目の午前は自由に過ごし、午後、ルーブル美術館に入る。まず最初にヘレニズム芸術の傑作、サモトラケの勝利の女神ニケとミロのヴィーナスが出迎える。ニケには顔がないのが残念であるが、ヴィーナスの端正な顔は見ていて飽きない。さらに飽きないのは理想的な形の乳房で、誰もいなければ触れたくなる衝動にかられる。広いホールが続き、学生時代の美術教科書でみた絵がすべてある。展示品の総数は20万を超え、目録品数は40万という膨大なコレクションである。ナポレオンは戦利品として獲ってきたあとも、敗戦国に美術品を要求し続けた。 モナリザは確かに謎めいて見える。彼女のかすかな微笑をめぐって、聡明な哲学的微笑みか、あるいは意地悪女の薄笑いかを論じる向きもあるが、後者はおそらく俗筋の深読みというものであろう。女というのはわからないというが、ダヴィンチであるから次元の低い発想などしなかったとは思う。
モナリザは確かに謎めいて見える。彼女のかすかな微笑をめぐって、聡明な哲学的微笑みか、あるいは意地悪女の薄笑いかを論じる向きもあるが、後者はおそらく俗筋の深読みというものであろう。女というのはわからないというが、ダヴィンチであるから次元の低い発想などしなかったとは思う。野上弥生子は「欧米の旅」(岩波文庫)でそんな議論には耳をかさず、まったく異なった視点でこの不思議な女性を観察していた。
| 彼女が今もし声をだしたら、どんな声を出すだろう。私はふとそんなことを考えて見たが、声柄も調子も想像されなかった。むしろ彼女はフィレンツェにすんでいたあいだも、決して口は利かなかった女のような気がする。単に「ええ」とか「いいえ」とかさえも云わず、かすかにうなずくか、首をふるだけで、すべてはこの微笑で、人間がもっている限りの言葉を使う以上の思想感情を示していたのであろう。 |
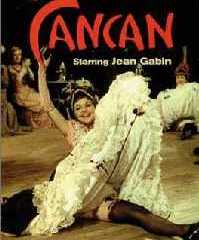 夜はカジノ・デ・パリでフレンチ・カンカンを見た。60フラン(約4000円)の入場料は旅行費に含まれている。同名の映画でもなじみの、フリルのスカートの裾をまくりあげて脚をこれでもかとふりあげる、あのアケスケな色気は見ていても気持ちがよい。
夜はカジノ・デ・パリでフレンチ・カンカンを見た。60フラン(約4000円)の入場料は旅行費に含まれている。同名の映画でもなじみの、フリルのスカートの裾をまくりあげて脚をこれでもかとふりあげる、あのアケスケな色気は見ていても気持ちがよい。4日目は終日自由行動で、ランチ代として現金が配られた。地下鉄メトロに乗って町を移動しようとしたが複雑な切符自動販売機にてこずった。英語の通じないこの町は最後まで馴染めなかった。大学で2年間習ったフランス語など、なんの役にも立ちはしない。
オペラ座、ロダン美術館、その隣のナポレオンの墓、学生の溜まり場カルチェ・ラタン、実存主義者の溜まり場サンジェルマン・デ・プレ、ボヘミアンの溜まり場モンパルナスなどを無目的的に見て回る。ロートレックやユトリロの絵を彷彿とさせる、ムーラン・ルージュの水車があるあたりは歓楽街である。
 今はどうだか知らないが当時のパリでは売春は合法で、夜の女の労働組合があった。パリに入った初日の夜、バスの窓から大通りにたむろする女性を指して、ヴィエナから来たグループ・リーダーが「今彼女らは、年金制度の適用を求めて、スト決行中なのだ」と説明した。売春婦のストライキが社会的にどれほど効果があるものか、聞くのを忘れた。
今はどうだか知らないが当時のパリでは売春は合法で、夜の女の労働組合があった。パリに入った初日の夜、バスの窓から大通りにたむろする女性を指して、ヴィエナから来たグループ・リーダーが「今彼女らは、年金制度の適用を求めて、スト決行中なのだ」と説明した。売春婦のストライキが社会的にどれほど効果があるものか、聞くのを忘れた。夜は豪華なフレンチ・ディナーであった。たっぷりとガーリックに浸したカタツムリと、胡椒をきかせたステーキが出た。
パリ観光はフランス革命の知識を装備しておかなければ10分の1の値打ちもない。私は建物や風景の形に興味があったので写真を撮るだけで目的を果たしたつもりであったが、莫大な歴史・文化の鑑賞を怠った。シェイクスピアの作品を読んだこともなくてストラト・アポン・エイヴォンを見たり、日本古代史を知らないで奈良を歩いているようなものである。仮に知識があったとしたらなおのこと、3日でパリを鑑賞するなど不可能である。結局頭の中は未消化情報の洪水のまま、パリを離れることになった。
 パリで買ったみやげのレシートが残っている。エデンという店で、淡いピンクの足つきの皿と、ロイヤル・ブルーの小さな手鏡と、ネクタイを1本買ってある。値段は夫々、416、16、35フラン、日本円にして、27000円、1000円、2300円であった。
パリで買ったみやげのレシートが残っている。エデンという店で、淡いピンクの足つきの皿と、ロイヤル・ブルーの小さな手鏡と、ネクタイを1本買ってある。値段は夫々、416、16、35フラン、日本円にして、27000円、1000円、2300円であった。 5日目の朝、パリの西20kmにあるヴェルサーユへ移動する。ヴェルサーユには17世紀後半、ルイ13世の狩の小城があったのみであったが、太陽王ルイ14世の時代になって王宮がルーブルから移され、以降フランス革命まで絶対王権の栄華の舞台となった。バロック様式建築の代表作である。
5日目の朝、パリの西20kmにあるヴェルサーユへ移動する。ヴェルサーユには17世紀後半、ルイ13世の狩の小城があったのみであったが、太陽王ルイ14世の時代になって王宮がルーブルから移され、以降フランス革命まで絶対王権の栄華の舞台となった。バロック様式建築の代表作である。 広大な庭園を前に、長く横たわる壮麗な宮殿の前面は580mにも及ぶ。中は豪華絢爛な居間が次から次へと続き、そのうちの1つである鏡の間で1919年、第一次大戦後の平和条約が締結された。ヴェルサーユの庭園は遠近法を巧みに取り入れた幾何学模様の設計になっていて、典型的なフランス式庭園である。余りに広すぎて、バスの待ち時間のあいだに歩いてみて廻ろうという考えが起こってこない。ただ、地平線の一点に消えて行かんばかりの人工空間を眺めているだけという具合であった。
広大な庭園を前に、長く横たわる壮麗な宮殿の前面は580mにも及ぶ。中は豪華絢爛な居間が次から次へと続き、そのうちの1つである鏡の間で1919年、第一次大戦後の平和条約が締結された。ヴェルサーユの庭園は遠近法を巧みに取り入れた幾何学模様の設計になっていて、典型的なフランス式庭園である。余りに広すぎて、バスの待ち時間のあいだに歩いてみて廻ろうという考えが起こってこない。ただ、地平線の一点に消えて行かんばかりの人工空間を眺めているだけという具合であった。ロワール谷
午後は更に南に下って、フランスの城と庭の地方、ロワール川沿いの古城巡りをすることになった。温暖、肥沃なロワール川に沿って、16世紀から18世紀の美しい城が点在する。城の屋根は丸味を帯びた円錐形で、ロンドンでみるチェスのルーク状の円柱形に比べると女性的な優しく優雅なたたずまいである。周辺はロンドン郊外の田園とは違った明るさがあり、ミレーの絵にある風景が広がっている。ブロワ城、アンボワーズ城を見て、シュヌーソに泊まる。
夜、星と月の光の下で、お伽話にあるようなロマンティックなシュヌーソの城の「音と光のスペクタクル」を楽しんだ。7色のスポットライトと音楽のなかで、野外のナレーションが私たちを過去にいざなう。言っていることはよく分からなかったが、「6人の女の城」といわれているので、おそらくそのことであろうと想像をめぐらし昔の気分を味わった。
6人の内3人はわかっている。
 1513年、ノルマンディの副財務長官であったトーマス・ボイヤがシェー川沿いの旧宅地を買ってそこに城を建てはじめた。10年後にボイヤーは死に、妻のカトリーヌ・ブリソネットがけなげに工事を続けたが結局相続税の支払いのため、時の国王フランソワ一世に売らねばならなかった。次の国王アンリ2世はその城を愛人のダイアン・ドゥ・ポワチエに贈った。ダイアンは建築家フィリプ・デロルムを雇って美しい庭を造ったほかシェー川に立派なアーチの橋を架けた。まもなくアンリ2世が死ぬと正妻のカトリーヌ・ドゥ・メディチはその魅力ある城をダイアンから奪い取った。カトリーヌはデロルムに命じて、ダイアンが架けた橋の上に回廊を設けた。仲の悪かった2人の貴婦人の共同作業で華麗で魅惑的なシュヌソー城が完成したのである。
1513年、ノルマンディの副財務長官であったトーマス・ボイヤがシェー川沿いの旧宅地を買ってそこに城を建てはじめた。10年後にボイヤーは死に、妻のカトリーヌ・ブリソネットがけなげに工事を続けたが結局相続税の支払いのため、時の国王フランソワ一世に売らねばならなかった。次の国王アンリ2世はその城を愛人のダイアン・ドゥ・ポワチエに贈った。ダイアンは建築家フィリプ・デロルムを雇って美しい庭を造ったほかシェー川に立派なアーチの橋を架けた。まもなくアンリ2世が死ぬと正妻のカトリーヌ・ドゥ・メディチはその魅力ある城をダイアンから奪い取った。カトリーヌはデロルムに命じて、ダイアンが架けた橋の上に回廊を設けた。仲の悪かった2人の貴婦人の共同作業で華麗で魅惑的なシュヌソー城が完成したのである。6日目も古城巡りを続ける。16世紀、フランソワ1世に愛用されたシャンボール城は5ヘクタール、周囲35kmのフェンスで囲まれた狩猟場の中にある。地平線がみえるほどの平坦な原にポツンとひとつ、多数の華麗な塔を頂いた横長の城が、前の大きな堀池にその姿を映している。
ロワールで最も大きなこの城は、
と形容されている。もう少し正確にいうと多数の華麗な塔は「寝起きざまのくせ毛」のようなのだ。内も外も左右が全く対称に造られている。比較的装飾の少ない外観に比べて内装はルネサンス調の豪華なものだった。とくに二重階段は有名で下から上まで、降りる人と登る人が互いに見合うことがないように作られている。
シャンボール城を見たあと、肥沃なフランスの農村地帯を北上する。幾度となくドイツとの間で争奪戦を繰り返したザール・ロレーヌ地方の国境の町ザールブリュッケンを越えて、夜ハイデルベルクに着く。
トップへ
3.ハイデルベルク
7日目、1日を中世の古城と大学の町で過ごす。ハイデルベルグ城は13世紀に建てられたファルツ選帝侯の居城で、ヨーロッパでも最も美しいとされる城跡である。城は小高い丘の上にあり、 そこから見下ろすハイデルベルグの町は一幅の絵そのものであった。ラインの支流、ネッカー川に赤茶けたカール・テオドール橋が架かる。流麗なアーチを描くその石橋はアルテ・ブリュッケ(古い橋)として親しまれている。川の両側に広がる町の屋根も赤茶色の瓦に統一されていて、景観を乱すものがない。川の向こうの丘の中腹には「哲学者の道」があるという。京都の哲学の道のルーツである。東山から見下ろす木造の家と黒い瓦の京都の町を、赤瓦のレンガ造りにしたような趣であった。否、それよりも美しい。
そこから見下ろすハイデルベルグの町は一幅の絵そのものであった。ラインの支流、ネッカー川に赤茶けたカール・テオドール橋が架かる。流麗なアーチを描くその石橋はアルテ・ブリュッケ(古い橋)として親しまれている。川の両側に広がる町の屋根も赤茶色の瓦に統一されていて、景観を乱すものがない。川の向こうの丘の中腹には「哲学者の道」があるという。京都の哲学の道のルーツである。東山から見下ろす木造の家と黒い瓦の京都の町を、赤瓦のレンガ造りにしたような趣であった。否、それよりも美しい。 城のなかに世界で最大のワイン樽が隠されている。22万リットル入りというから、1升瓶12万本分のワインが入る。2階建ての家ほどもある、とにかくも大きい。これを作った者はかなりのいたずら心の持ち主だったにちがいないと思えた。
城のなかに世界で最大のワイン樽が隠されている。22万リットル入りというから、1升瓶12万本分のワインが入る。2階建ての家ほどもある、とにかくも大きい。これを作った者はかなりのいたずら心の持ち主だったにちがいないと思えた。ハイデルベルグは学生の町である。ハイデルベルグ大学は1386年創設のドイツ最古の大学で、マイヤー・フェルスター作「アルトハイデルベルグ」の主人公、ハインリッヒ王子が学んだ大学である。16世紀後半から17世紀初期にかけて、ドイツの学芸文化と宗教改革の中心であった。
ランチを、中世風の学生宿セプルでとる。おかずはザウアークラウトとソーセージで、メインは大ジョッキーのビールである。大学生の溜まり場であるここでは、バンカラ風にふるまうのが礼儀というもので、古いドイツの学生歌「Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren」(I lost my heart in Heidelberg )を、ジョッキーを掲げて放歌する。意味もわからず雰囲気にのまれて唄ったがコンパをやっているようで楽しかった。ドイツ語はともかく英語訳はこんな歌詞である。
| It was a summer evening, Just twenty I had seen, When I kissed ruby lips and Hair of golden sheen. The night was blue and blissful, The Neckar flowed pristine, It was then I knew, it was then I knew, What all to me did mean.. |
I lost my heart in Heidelberg for all time, On a balmy summer night. In love head over heels, oh were she all mine, And like a rose, her laughing mouth my light. As by the gates she said: "Good-bye my lover," That last sweet kiss, it did confirm once more, I'd lost my heart in Heidelberg forever. My heart still beats on Neckar's shore. |
建物の壁にはセピア色をしたフラターニティの写真がところかまわず貼り付けてある。ハイデルベルグの町は人口14万人ほどであるが、その10分の1(最近の情報では5分の1)が大学生だという。京都も学生の町で、「学生はん」は好意的に受け入れられる土壌がある。ネッカー川を鴨川とし、古い橋を三条大橋とすれば、ますますビルを取り除いた京都に似て、私はハイデルベルグが好きになった。
町単位で今回のヨーロッパ旅行を総括すれば、第1位がヴェネチアで、2位がハイデルベルグである。
トップへ
4.スイス

スイスの面積は4万1000平方キロで、オランダ、デンマークとほぼ同じ、九州よりやや広い。1スイス・フランは0.41ドルで約120円であった。この国は4つの言語圏からなり、フランス語、ドイツ語、イタリア語、そしてロマンシュ語が話されている。私たちの行くところはドイツ語圏である。国の印象として、スクラップ・ブックのメモから引用すると、
| Unfriendly People People Army きれいな牧草、小さな教会、 素朴なキリスト像(丸太作り、色彩豊か) |
またアンフレンドリーとは単に女性の態度だけで判断したわけではない。実はここだけの話しだが、スイスは「世界3大ブス国」の1つと言われているそうだ。アジアやアフリカの女性も含めての話かどうか、確かでないので、ここで世界とはヨーロッパのこと、あるいは白人国のことであると注釈しておこう。他の2つはポルトガルと、確かオランダであったと思う。
反対に美人国はチリとイランだと言われている。国際機関による統計があるわけではないので、このランキングについての責任は持てない。ただ日本における秋田美人に何らかの根拠があるのであれば、先の話しにも同じ程度の根拠があってもいいのではと思っただけである。
 8日目はハイデルベルグから時速制限無しのオートバーンを走ってスイスに入り、バーゼルを経て昼ごろルーツェルンへ着いた。スイス中央部に位置し、海抜436m、人口7万人の小さな町である。スイスといえばジュネーブを根拠にしたカルビンの宗教改革を思い起こすが、ここルーツェルンはそれに対抗したカソリック・レジスタンスの本拠地であった。ウィリアム・テルの伝説が生まれたことでも知られているように保守的な土地柄である。
8日目はハイデルベルグから時速制限無しのオートバーンを走ってスイスに入り、バーゼルを経て昼ごろルーツェルンへ着いた。スイス中央部に位置し、海抜436m、人口7万人の小さな町である。スイスといえばジュネーブを根拠にしたカルビンの宗教改革を思い起こすが、ここルーツェルンはそれに対抗したカソリック・レジスタンスの本拠地であった。ウィリアム・テルの伝説が生まれたことでも知られているように保守的な土地柄である。 ここではランチ代を貰っただけで、特別なプログラムはない。自由に昼食をとって、静かな中世の香りが漂う湖畔の町をみて歩くだけである。石畳の小路には山小屋風のホテルやレストランが立ち並び、時計やオルゴールなど、スイスのみやげ品が勢揃いしていた。スワォッチは子供っぽくて高級時計というスイスのイメージには合わない。貝殻を埋めたオルゴール箱や、しかけ人形付きのハト時計など、欲しい土産品があったが、いずれも予定の小遣いからは捻出できない値段であったので、地味なスイス人形とヨーデルのミュージックテープで我慢することにした。
ここではランチ代を貰っただけで、特別なプログラムはない。自由に昼食をとって、静かな中世の香りが漂う湖畔の町をみて歩くだけである。石畳の小路には山小屋風のホテルやレストランが立ち並び、時計やオルゴールなど、スイスのみやげ品が勢揃いしていた。スワォッチは子供っぽくて高級時計というスイスのイメージには合わない。貝殻を埋めたオルゴール箱や、しかけ人形付きのハト時計など、欲しい土産品があったが、いずれも予定の小遣いからは捻出できない値段であったので、地味なスイス人形とヨーデルのミュージックテープで我慢することにした。 ロイス川にはカペル橋という瓦屋根付きの木橋が架かり、その中央どころに8角柱のワッサートゥルムという水の塔が水面から突き出ている。古びた木の橋げたはベゴニアの花で飾られていて、橋というより川を横切る渡り廊下を歩いている気分であった。町の屋根並みの上はすべて、雪をいただくスイスアルプスの峰の連なりである。

 その日の宿はルーツェルンの西方にあるエントルバッハという静かな小村の、スキーリゾートの民宿風ホテルであった。店は早々と6時にしまるのでそこは夕食と寝るためだけのものである。夜、燭の灯のもとで、スイス・ビーフ・フォンデュを楽しんだ。角ぎりのビーフを自分のテンダネスに揚げ、10種類以上もあるソースのなかから好きなものを選んで浸ける。普通のスイス・チーズ・フォンデュよりも格段に上等で、美味しい。食堂の真中で、羽つき登山帽と民族衣装で身を包んだおじさんたちが、3m先の床に置かれたタバコを長大キセルで吸うように、長いホーンで地元のフォークソングを演奏してくれた。
その日の宿はルーツェルンの西方にあるエントルバッハという静かな小村の、スキーリゾートの民宿風ホテルであった。店は早々と6時にしまるのでそこは夕食と寝るためだけのものである。夜、燭の灯のもとで、スイス・ビーフ・フォンデュを楽しんだ。角ぎりのビーフを自分のテンダネスに揚げ、10種類以上もあるソースのなかから好きなものを選んで浸ける。普通のスイス・チーズ・フォンデュよりも格段に上等で、美味しい。食堂の真中で、羽つき登山帽と民族衣装で身を包んだおじさんたちが、3m先の床に置かれたタバコを長大キセルで吸うように、長いホーンで地元のフォークソングを演奏してくれた。9日目はアルプス山中を縫うようにイタリア国境付近まで移動する。ウィリアム・テルが息子の頭においたリンゴを射ったというスイスの英雄伝説がつたわるルーツェルンの湖畔にそって険しい坂を上がっていくと、行く手にアルプスの峰がそびえてくる。
 右手西方にアイガー(3970m)、メンヒ(4099m)やユングフラウ(4158m)の雄大な姿が見える峠に、ローヌ氷河がある。ローヌ川がここから発し、フランス東南部を南下してアヴィニオンを通り、マルセーユの西で地中海に注いでいるのだ。青白く濁った氷河を見下ろしながらパンとコークのピクニックランチをとる。数種類のハムやソーセージをフレンチ・パンにねじ込んで、そのまま噛みつくのは爽快であった。「サウンド・オヴ・ミュージック」でエプロン・ドレスのジュリー・アンドリュースと7人の子供が高原でピクニックに遊ぶ風景の中に私たちもいた。
右手西方にアイガー(3970m)、メンヒ(4099m)やユングフラウ(4158m)の雄大な姿が見える峠に、ローヌ氷河がある。ローヌ川がここから発し、フランス東南部を南下してアヴィニオンを通り、マルセーユの西で地中海に注いでいるのだ。青白く濁った氷河を見下ろしながらパンとコークのピクニックランチをとる。数種類のハムやソーセージをフレンチ・パンにねじ込んで、そのまま噛みつくのは爽快であった。「サウンド・オヴ・ミュージック」でエプロン・ドレスのジュリー・アンドリュースと7人の子供が高原でピクニックに遊ぶ風景の中に私たちもいた。午後はさらに雄大なキラー氷河に降り立つ。空気が一段と冷たくなる。数10年前、近くの貯水池を建設中に、氷河の一部が崩れ、刃のように鋭い氷の破片が工事中の作業員88名に一瞬のうちに切り込んだ。それから「人殺し氷河」とよぶようになったという。
 ビスプという町で左折し、シュタルデンでさらに左側の谷道をとるとやがてドーム(4545m)とワイスミース(4023m)に取り囲まれた山里ザース・アルマゲルという人口わずか300人の小さな谷村に到着する。海抜は1672mで、ビッグホーン山羊が峰近くで草を食んでいる。石造りの谷間の教会が1軒、その他は3階ないし4階建ての山小屋民宿風の民家である。翌日の山登りのために来たのであった。
ビスプという町で左折し、シュタルデンでさらに左側の谷道をとるとやがてドーム(4545m)とワイスミース(4023m)に取り囲まれた山里ザース・アルマゲルという人口わずか300人の小さな谷村に到着する。海抜は1672mで、ビッグホーン山羊が峰近くで草を食んでいる。石造りの谷間の教会が1軒、その他は3階ないし4階建ての山小屋民宿風の民家である。翌日の山登りのために来たのであった。10日目は1日をかけての日帰り登山となった。皆と一緒であればつらくない。高くなるにつれ精神的な自由が広がってくるのを感じる。スイスアルプスに囲まれて、あたりは静寂に包まれている。空気は薄く人の声もささやきに聞こえて余計に静かだった。歴史や文化やカメラのことは全部忘れて、ただ山を登って高きを目指すことに集中する。改めて、教育的なツアーだなあと思ったりした。
11日目、昨日きた道をブリークまで引き返し、そこを右に折れていよいよシンプロン峠を越えてイタリーに向かう。そびえたつ絶壁や吸い込まれるような深い谷を縫ってアルプス山地を降りたところがミラノで、そこからロンバルディア平原の北縁をつたうように東に走り、アドリア海に達したところにヴェニスがある。
トップへ
5.イタリア 
| 陽気‐商売気‐値引き交渉、日本語の話せるガイド、店員。 Vino(Rosso‐red、Bianco ‐White) 寺院見学(ノースリーブ、短パン、超ミニ厳禁) ディスコ‐ イタリアーノのしつこい女勧誘 コミュニストの躍進 6/20 総選挙 34%(キリスト民主党 38%) コイン不足、つり銭としてガムor地方の銀行券(他地方では通用せず) |
 減な国なのである。
減な国なのである。ところで、イタリアについて良いことを1つ忘れていた。男も女も、おしなべて子供がかわいい。通りで遊んでいる子供はみんな「鉄道員」に出てくる子役のようで、だれでもオーディションなしに映画に出られそうな顔つきをしている。イギリスやフランスでみた子供たちとははっきり違う。粒が揃っていて、不作がない。これは驚くべき発見であった。このようなすばらしい子供たちが大人になるにつれ、いつのまにかいいかげんな人間になっていく。
ヴェニス(ヴェネチア)
 12日目は終日ヴェニスである。人口37万人の水の都は118の小島の上に117の運河が走り、400の橋でつながっている。道は運河で、車はゴンドラである。サンタルチア駅からカナル・グランデがS字形にくねり海の出口でカナル・ディ・サン・マルコに変わる。カナル・グランデの両岸にヴェニスのすべてがあるといっても過言ではない。
12日目は終日ヴェニスである。人口37万人の水の都は118の小島の上に117の運河が走り、400の橋でつながっている。道は運河で、車はゴンドラである。サンタルチア駅からカナル・グランデがS字形にくねり海の出口でカナル・ディ・サン・マルコに変わる。カナル・グランデの両岸にヴェニスのすべてがあるといっても過言ではない。 中央に架かる橋が16世紀に建造されたリアルト橋で、両岸からゆるやかな傾斜をもって寄りあがり、中央で方形の巨大な宙づり籠で接着されているような構造をしている。瓦屋根つきの石作りで、欄干にかわって左右に6つのアーチが並んで美しい。両岸は商業地区の中心で、橋の上も貴金属や革製品の店屋が隙間なく埋めていた。みな私に日本語で売り込んでくる。スイスのそっけない店員も気分よくないが、商売気がありすぎるもの困ったものである。中庸というのはむずかしい。強いて言えばロンドンの店員はそうではなかったかと思われた。
中央に架かる橋が16世紀に建造されたリアルト橋で、両岸からゆるやかな傾斜をもって寄りあがり、中央で方形の巨大な宙づり籠で接着されているような構造をしている。瓦屋根つきの石作りで、欄干にかわって左右に6つのアーチが並んで美しい。両岸は商業地区の中心で、橋の上も貴金属や革製品の店屋が隙間なく埋めていた。みな私に日本語で売り込んでくる。スイスのそっけない店員も気分よくないが、商売気がありすぎるもの困ったものである。中庸というのはむずかしい。強いて言えばロンドンの店員はそうではなかったかと思われた。 ヴェニスの中心はサン・マルコ広場で、サン・マルコ大寺院とドゥカーレ宮殿が並んでいる。上野公園のように鳩が頭の上を飛びまわるのもここである。サン・マルコ大寺院は9世紀から11世紀にかけて建てられ、ビザンチンとロマネスクの混合様式である。さらにナルテックスという、本堂に入れないもののために作られた拝堂はゴシック風で、ロンドンやパリでみた大聖堂に比べると国際色豊かで、エキゾチックな匂いがあった。
ヴェニスの中心はサン・マルコ広場で、サン・マルコ大寺院とドゥカーレ宮殿が並んでいる。上野公園のように鳩が頭の上を飛びまわるのもここである。サン・マルコ大寺院は9世紀から11世紀にかけて建てられ、ビザンチンとロマネスクの混合様式である。さらにナルテックスという、本堂に入れないもののために作られた拝堂はゴシック風で、ロンドンやパリでみた大聖堂に比べると国際色豊かで、エキゾチックな匂いがあった。上層中央には紀元前4世紀頃の作といわれる、4つの青銅馬像がみごとな躍動美をみせている。ナポレオンが1度はこの馬像をパリに持ち帰ったが、良心が咎めて返してきたいわくつきのものである。そもそもこの青銅馬像はヴェネチア人が13世紀はじめ、コンスタンチノープルの競技場から持ち帰ってきたものだというから、ナポレオンに取られていたとしても文句はいえない。
 ドゥカーレ宮殿はヴェネチア共和国総督の館である。サン・マルコ大寺院とおなじく最初は9世紀にビザンチン様式で建てられたが、15世紀になって今のような堂々たるゴシック様式の外観になった。アーケードを支える36本の円柱と、さらにその上にある回廊の71本の円柱が整然と並んでいる。壁を飾る幾何学的模様とも相俟って、建物の計算された科学性はイスラム芸術とダヴィンチの生真面目さを連想させるほどであった。
ドゥカーレ宮殿はヴェネチア共和国総督の館である。サン・マルコ大寺院とおなじく最初は9世紀にビザンチン様式で建てられたが、15世紀になって今のような堂々たるゴシック様式の外観になった。アーケードを支える36本の円柱と、さらにその上にある回廊の71本の円柱が整然と並んでいる。壁を飾る幾何学的模様とも相俟って、建物の計算された科学性はイスラム芸術とダヴィンチの生真面目さを連想させるほどであった。 この建物と獄舎の間を、細い運河を跨いで「ため息の橋」と呼ばれる短く狭い橋がつないでいる。小さな窓があるほかは壁に塞がれた日の射さない暗い橋である。中世の時代、この橋を囚人が渡る時、自分の最期が来たことを知って、その小さな窓からヴェニスの町を見納めて、深くて長い溜息をついた。
この建物と獄舎の間を、細い運河を跨いで「ため息の橋」と呼ばれる短く狭い橋がつないでいる。小さな窓があるほかは壁に塞がれた日の射さない暗い橋である。中世の時代、この橋を囚人が渡る時、自分の最期が来たことを知って、その小さな窓からヴェニスの町を見納めて、深くて長い溜息をついた。ガラス工場を見学した。赤くとけた水飴状のガラス玉を長い管から吹いて、みごとなヴェネチア・グラスを作り上げる。職人の目は真剣であった。独特の深い赤ワインの色をしたヴェネチアンレッドと、アドリア海のヴェネチアンブルーと呼ばれる透き通った極彩色のグラスは格別である。
ヴェネチアの建物の色は、くすんだワイン・レッド、マスタード・イエロー、サーモン・ピンク、薄レンガ色など全体に淡い暖色系でまとめられていて、目にやさしい。
 昼下がりのひとときをリドのビーチで水遊びして、気だるい体を夜、月光のゆらめきに浮かぶゴンドラに沈める。5、6人毎にゴンドラに乗り込み、ギタリストがロマンティックなムードを盛り上げる。もしこれが一人旅であったなら、しかも女の1人旅であったなら、と考えさせるのはキャサリーン・ヘプバーンの「旅情」のせいであろう。原題は「サマータイム」である。
昼下がりのひとときをリドのビーチで水遊びして、気だるい体を夜、月光のゆらめきに浮かぶゴンドラに沈める。5、6人毎にゴンドラに乗り込み、ギタリストがロマンティックなムードを盛り上げる。もしこれが一人旅であったなら、しかも女の1人旅であったなら、と考えさせるのはキャサリーン・ヘプバーンの「旅情」のせいであろう。原題は「サマータイム」である。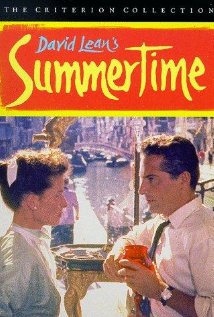 長い秘書生活で婚期を逸したキャリア・ウーマンが8ミリカメラをぶら下げてヴェネチアの町にやってきた。ワインと鳩と陽気なイタリア人に囲まれて旅情を楽しむが、心にはなにかヴェネチアの魅力をもってしても満たされない隙間がある。その隙間を埋めるように、ある中年男性と知り合い食事を共にする。
長い秘書生活で婚期を逸したキャリア・ウーマンが8ミリカメラをぶら下げてヴェネチアの町にやってきた。ワインと鳩と陽気なイタリア人に囲まれて旅情を楽しむが、心にはなにかヴェネチアの魅力をもってしても満たされない隙間がある。その隙間を埋めるように、ある中年男性と知り合い食事を共にする。 「アメリカ人ならランを選ぶのだけれど…」と、花売りから彼女が買ったのはくちなしの花だった。世間なみに、彼には妻子がいた。ジェーンはヴェネチアとつかの間の夏の恋を思い出に、魅惑的な町を去ることに決める。駅には1輪のくちなしの花を掲げて追いかける男の姿があった。
「アメリカ人ならランを選ぶのだけれど…」と、花売りから彼女が買ったのはくちなしの花だった。世間なみに、彼には妻子がいた。ジェーンはヴェネチアとつかの間の夏の恋を思い出に、魅惑的な町を去ることに決める。駅には1輪のくちなしの花を掲げて追いかける男の姿があった。「来てくれたのね。……うれしい……」
1人旅の孤独を好むロマンチシズムには、逆説的なほろ苦い自己満足か、気づきたくない寂しさのカモフラージュである場合が多い。
フローレンス(フィレンツェ)
13日目はヴェネチアをあとに、世界最古の大学の町ボローニャを通過して、メディチ家とミケランジェロの町、フローレンスへ移動する。車窓の風景はロンドン郊外やロワール渓谷のようには美しくはないが、アテネ郊外ほど乾いてはいない。
フローレンスは人口46万人で、ヴェネチアよりも10万人多い。イタリア芸術と文化の中心であるフローレンスはルネッサンス発祥の地で、それを支えたのがメディチ家の富であった。15世紀に最盛期を迎える。細い通りに巨大なパレスが中世の雰囲気をのこしている。町を分断して流れるアルノ川は10年前大洪水を起こし、町に手痛い被害を与えたが、国際的な援助もあって今その爪痕は見られなかった。
14日目と15日目の午前にかけて市内を見て歩く。パリのように新旧が混在していない。ただただ中世の美術鑑賞をするのみである。
 ドゥオモ(大聖堂)はまたの名を「サンタ・マリア・デル・フローレ(花のサンタ・マリア)」ともいわれ、巨大な赤い丸屋根を頂く。この大円蓋(キューポラ)はブルネレスキーが1420年から14年の歳月をかけて製作した建築史上に名を残す傑作であるという。およそ1世紀後、ミケランジェロがローマのセイント・ピーター寺院を建てるときこのドームを参考にした。ドームを作ったのはよいがこれを上に乗せるのがまた大変な苦労であったらしい。外観は灰グリーン、ピンク、白の大理石で幾何学的なデザインがなされている。個人的にはあまり好きな配色ではない。
ドゥオモ(大聖堂)はまたの名を「サンタ・マリア・デル・フローレ(花のサンタ・マリア)」ともいわれ、巨大な赤い丸屋根を頂く。この大円蓋(キューポラ)はブルネレスキーが1420年から14年の歳月をかけて製作した建築史上に名を残す傑作であるという。およそ1世紀後、ミケランジェロがローマのセイント・ピーター寺院を建てるときこのドームを参考にした。ドームを作ったのはよいがこれを上に乗せるのがまた大変な苦労であったらしい。外観は灰グリーン、ピンク、白の大理石で幾何学的なデザインがなされている。個人的にはあまり好きな配色ではない。横に立つのが1359年完成のジョットの鐘楼で、高さ82m、上がろうとすれば290段の階段がある。335段の階段を上って自由の女神の冠から顔を出している人たちがいるが、彼らは途中までエレベーターで上がって来ている。ここの鐘楼にはそのような近代的設備はないので、地上から歩かねばならない。誰も上がろうとするものはいなかった。
 ドゥオモの対面に8角形のサンジョバンニ洗礼堂がある。12世紀、ロマネスク様式の教会で、浮き彫りを施した3つの青銅扉が3方の入口を飾っている。なかでもドゥオモに面した東側の第2の青銅扉はギベルディが1425年から27年かけて製作したもので、ミケランジェロから「天国の門」と激賞された傑作である。10のパネルにはアダムとイヴをはじめとして旧約聖書からとった題材の彫刻がはめられている。
ドゥオモの対面に8角形のサンジョバンニ洗礼堂がある。12世紀、ロマネスク様式の教会で、浮き彫りを施した3つの青銅扉が3方の入口を飾っている。なかでもドゥオモに面した東側の第2の青銅扉はギベルディが1425年から27年かけて製作したもので、ミケランジェロから「天国の門」と激賞された傑作である。10のパネルにはアダムとイヴをはじめとして旧約聖書からとった題材の彫刻がはめられている。 13世紀の創建といわれるサンマルコ修道院の斜め向かいにアカデミア美術館があり、1505年のミケランジェロの傑作、「ダヴィデ像」が立っている。これがオリジナルで、ベッキオ宮やミケランジェロ広場にあるのはそのコピーである。コピーといえばこれだけでなくて、ロダンの「考える人」やミロのヴィーナスも含めて、世界の色々な所で見たような気がする。ミロのヴィーナスはルーブルにあるものの他は贋物とわかるが、「ダヴィデ像」や「考える人」は製作者が作ったコピーなのか、後世の複製なのか、素人にはよく分からない。
13世紀の創建といわれるサンマルコ修道院の斜め向かいにアカデミア美術館があり、1505年のミケランジェロの傑作、「ダヴィデ像」が立っている。これがオリジナルで、ベッキオ宮やミケランジェロ広場にあるのはそのコピーである。コピーといえばこれだけでなくて、ロダンの「考える人」やミロのヴィーナスも含めて、世界の色々な所で見たような気がする。ミロのヴィーナスはルーブルにあるものの他は贋物とわかるが、「ダヴィデ像」や「考える人」は製作者が作ったコピーなのか、後世の複製なのか、素人にはよく分からない。 「ダヴィデ像」に出会うたびに自分にいいきかせることがある。――芸術だから恥ずかしくない、と。ギリシャとローマ彫刻の鑑賞にはこれが避けて通れないのだが、日本人にはなれない光景であることは確かであろう。いちじくの葉で隠すのはわざとらしいし、その部分をのっぺらぼうにしたのでは気味が悪い。キリスト像のようにそこだけ布をまとうのもさまにならない。古代西洋文明の彫刻には男性美崇拝が基底に潜んでいるように思える。中世のキリスト教文化はそれを布で覆ったがルネサンスがその布を剥いでしまった。
「ダヴィデ像」に出会うたびに自分にいいきかせることがある。――芸術だから恥ずかしくない、と。ギリシャとローマ彫刻の鑑賞にはこれが避けて通れないのだが、日本人にはなれない光景であることは確かであろう。いちじくの葉で隠すのはわざとらしいし、その部分をのっぺらぼうにしたのでは気味が悪い。キリスト像のようにそこだけ布をまとうのもさまにならない。古代西洋文明の彫刻には男性美崇拝が基底に潜んでいるように思える。中世のキリスト教文化はそれを布で覆ったがルネサンスがその布を剥いでしまった。いろんなことを考えながら細い路地を歩いていく。通りを抜けた瞬間に巨大な大理石の建物に出くわす連続であった。メディチ・リッカルディ宮、ヴェッキオ宮、サンタクローチェ教会、ウフィツィ宮、ピッティ宮など。ウフィツィ宮はパリのルーブル宮と同じで、なかはイタリ最大の美術館になっていて、13世紀から18世紀までの作品が並んでいる。ボッチチェリの「ヴィーナスの誕生」、レオナルド・ダ・ビンチの「受胎告知」、ミケランジェロの「聖家族」など、中学の美術教科書の初めに出てくるような絵が多い。ルーブルに比べて、中世の宗教画の香りが高い分だけ興味が薄い。
ピッティ宮とウフィツィ宮の渡り廊下の役目をしていたのが「古い橋」といわれるヴェッキオ橋である。この橋は2層構造で1階が歩道橋、2階が商店街になっている。ヴェネチアのリアルト橋を水平にして、2階建てとし、店屋の裏側を川に突き出させて雑然とさせるとおおむねヴェッキオ橋になる。
14日目の夜は中世の町を見下ろす丘で、ピザとワインのパーティがあった。フローレンスの町を眺めると、ヴェッキオ宮の鐘楼とドゥオモのキューポラとジオットの鐘楼以外、高い建物がない。屋根はすべて赤茶色の瓦で、この統一のとれた平面的な均一の広がりは、緑が少ないぶんだけ、城から見たハイデルベルグの町よりも際立って見えた。

 翌日の朝は見残した市内観光と土産ショッピングにあてた。ここでも日本語が通じる。日本人を置いている店まであった。皮製品、骨董品、木彫製品などが多い。私は金粉とオリーブ・グリーンとクリムソンの赤の3色で縁どられて中央にバラの花が描かれた、すこし金持ち趣味の木盆を買った。7千リラで高いと思ったのだが3000円もしていない。
翌日の朝は見残した市内観光と土産ショッピングにあてた。ここでも日本語が通じる。日本人を置いている店まであった。皮製品、骨董品、木彫製品などが多い。私は金粉とオリーブ・グリーンとクリムソンの赤の3色で縁どられて中央にバラの花が描かれた、すこし金持ち趣味の木盆を買った。7千リラで高いと思ったのだが3000円もしていない。 ランチはフローレンスの郊外、アルノ川のほとりにある美しいルネッサンスの別荘、ヴィラ・ラ・マサ(Villa La Massa)でとることになっていた。このヴィラは現在も、あるイタリア人伯爵夫人の所有地である。豪華なイタリア料理で満腹したあと、午後はゆっくりとそこにある屋外プールで水泳に興じた。アメリカ人は例外なく水泳がうまい。小さい頃からサマー・キャンプで習うからであろうか。飛び込みも慣れたものである。
ランチはフローレンスの郊外、アルノ川のほとりにある美しいルネッサンスの別荘、ヴィラ・ラ・マサ(Villa La Massa)でとることになっていた。このヴィラは現在も、あるイタリア人伯爵夫人の所有地である。豪華なイタリア料理で満腹したあと、午後はゆっくりとそこにある屋外プールで水泳に興じた。アメリカ人は例外なく水泳がうまい。小さい頃からサマー・キャンプで習うからであろうか。飛び込みも慣れたものである。5時になってバスにもどり、永遠の都ローマに向かう。
ローマ
 人口270万人の大都市であるがパリにくらべれば3分の1に満たない。しかし歴史の古さと遺跡の数においては世界のどの都市にも負けない。2000年経った今も町を掘り続けていて、それは終わることがない。
人口270万人の大都市であるがパリにくらべれば3分の1に満たない。しかし歴史の古さと遺跡の数においては世界のどの都市にも負けない。2000年経った今も町を掘り続けていて、それは終わることがない。16日目は1日中、史跡の宝庫といわれるローマ市内の観光であった。そのなかで最大のものがコロセウムである。長幅188m、短幅156mの楕円形で高さは57mの4階建てである。3階まではアーチ構造で下から各々ドリス、イオニア、コリント式のギリシャ様式付け柱で装飾されている。名の由来は、かって近くにあった暴君ネロの金色の冠をいただいた巨像(コロスス)からきているという。
 72年、ベスパシアヌス皇帝の命により始められ、コロセウムの建設に従事していた3000人のユダヤ人奴隷が死んでいった。中に入ってアリーナを見下ろすと、地下の通路や部屋の仕切りがむきだしになっている。かっては、それらは床板で覆われていてそのなかには猛獣や奴隷剣闘士や犯罪人などが閉じ込められていた。ライオンに食われる奴隷の悲劇は小学校の本にも載っていた。劇を演じる役者たちは脚本が死を要求するときは、その通りに演じて死んだ。奴隷剣闘士の運命はカーク・ダグラス演じる「スパルタカス」で描かれている。ローマ最大の遺跡は華やかなローマ文明の影の遺跡である。
72年、ベスパシアヌス皇帝の命により始められ、コロセウムの建設に従事していた3000人のユダヤ人奴隷が死んでいった。中に入ってアリーナを見下ろすと、地下の通路や部屋の仕切りがむきだしになっている。かっては、それらは床板で覆われていてそのなかには猛獣や奴隷剣闘士や犯罪人などが閉じ込められていた。ライオンに食われる奴隷の悲劇は小学校の本にも載っていた。劇を演じる役者たちは脚本が死を要求するときは、その通りに演じて死んだ。奴隷剣闘士の運命はカーク・ダグラス演じる「スパルタカス」で描かれている。ローマ最大の遺跡は華やかなローマ文明の影の遺跡である。コロセウムの西には313年にコンスタンティヌス帝によって立てられた優雅な凱旋門がある。3つのアーチにはトライアヌス帝、ハドリアヌス帝、マルクス・アウレリウス帝の浮き彫りが飾られている。およそ1500年後に、ナポレオンはこの凱旋門を真似して、パリのエトワールに自分の凱旋門を建てた。
 ローマを舞台にした名画は多い。子供の頃兄の部屋で見た「スクリーン」という映画雑誌にデ・シーカという監督の名前とともに、私とあまり違わない子供のでてくる映画のスチール写真が並んでいた。大人になって見たその映画は、共に悲しいやりきれない映画であった。1つは「靴磨き」。他の1つは「自転車泥棒」。ともに終戦直後のローマを舞台にした傑作である。
ローマを舞台にした名画は多い。子供の頃兄の部屋で見た「スクリーン」という映画雑誌にデ・シーカという監督の名前とともに、私とあまり違わない子供のでてくる映画のスチール写真が並んでいた。大人になって見たその映画は、共に悲しいやりきれない映画であった。1つは「靴磨き」。他の1つは「自転車泥棒」。ともに終戦直後のローマを舞台にした傑作である。世情も落ち着いてローマにも新しい中央駅ができたころ、テルミニ(ターミナル)と呼ばれるその駅を舞台にしたデ・シーカの「終着駅」という映画が出た。もう貧乏がテーマではない。夫と子供を持つアメリカの人妻がイタリアの若者と恋におちた。ヴェネチアを舞台にした「旅情」を男女ひっくり返したような設定である。ジェニファー・ジョーンズのつぶらな瞳と、気弱そうにみえながらずうずうしいモンゴメリー・クリフトが印象的であった。

 同じ年に作られたもっと楽しい映画がある。世界の女性を魅惑したオードリー・ヘプバーンのデビュー作、「ローマの休日」である。監督はウィリアム・ワイラー。彼は人に悲しい思いをさせない。ハリウッド映画の使命は人を楽しませることにあることを一番わきまえた監督である。ソフトクリームを手にスペイン階段を降りてくるすがすがしいヘプバーン、ボッカ・デラ・ベーリタ広場の教会柱廊にある「真実の口」と呼ばれるライオンのような海神トリトーンの口に手を入れ、あわてて引っ込めるヘプバーン、そんな無邪気な王女さんをやさしく見守る新聞記者グレゴリー・ペックの都会的センス。最後の記者会見でみせる別離シーンの奥ゆかしさは私には耐え難い。
同じ年に作られたもっと楽しい映画がある。世界の女性を魅惑したオードリー・ヘプバーンのデビュー作、「ローマの休日」である。監督はウィリアム・ワイラー。彼は人に悲しい思いをさせない。ハリウッド映画の使命は人を楽しませることにあることを一番わきまえた監督である。ソフトクリームを手にスペイン階段を降りてくるすがすがしいヘプバーン、ボッカ・デラ・ベーリタ広場の教会柱廊にある「真実の口」と呼ばれるライオンのような海神トリトーンの口に手を入れ、あわてて引っ込めるヘプバーン、そんな無邪気な王女さんをやさしく見守る新聞記者グレゴリー・ペックの都会的センス。最後の記者会見でみせる別離シーンの奥ゆかしさは私には耐え難い。カラカラ浴場はコロッセオの南1キロのところにあり、アッピア旧街道の始点サンセバスティアーノ門に近い。紀元前216年に作られたローマ風呂は健康科学に則った合理的なシステムを備えていて、入浴だけでなく広く社交の場として5世紀まで使われていた。1600人を収容できたという。アッピア街道は紀元前312年にナポリの近くまで作られたがその後ギリシャへ通じる港町タラントまで延長された幹線道路である。一部には轍の跡が残る石畳の道が古代ローマ時代そのままに保存されている。
 1960年のローマオリンピックのとき、エチオピアから来た哲学者アベベはこの街道を裸足で走って、息も乱れぬ思索に満ちた顔でテープを切った。カラカラ浴場やアッピア街道という言葉が盛んにテレビから流れていたのを覚えている。この街道沿いにカタコンベがある。初期のキリスト教徒がローマ人の迫害から逃れるため、地下に迷路のような通路を堀り、そこを墓としたものである。このあたりには25ヶ所ほどものカタコンベがあり、延々と張り巡らされた地下通路の総延長は500kmにもおよぶという。所々に礼拝所や納骨堂が点在していて貴重な歴史の証人とはいえ、気持ちの良いものではなかった。
1960年のローマオリンピックのとき、エチオピアから来た哲学者アベベはこの街道を裸足で走って、息も乱れぬ思索に満ちた顔でテープを切った。カラカラ浴場やアッピア街道という言葉が盛んにテレビから流れていたのを覚えている。この街道沿いにカタコンベがある。初期のキリスト教徒がローマ人の迫害から逃れるため、地下に迷路のような通路を堀り、そこを墓としたものである。このあたりには25ヶ所ほどものカタコンベがあり、延々と張り巡らされた地下通路の総延長は500kmにもおよぶという。所々に礼拝所や納骨堂が点在していて貴重な歴史の証人とはいえ、気持ちの良いものではなかった。
 午後はローマの東30km余り行ったヴィラ・デステを見た。ローマを囲む丘の上に、400年前に建てられたルネッサンス時代の別荘である。元はベネディクト派の修道院だったものを枢機卿イッポリト・デステが豪華な別荘に造営した。ここには「100の噴水」、「オルガン噴水」など数百もの噴水が作られていて、様々な工夫がこらされている。隠し噴水から突如として水が飛び出し、庭を散策する人をずぶぬれにさせたり、噴水があつまって滝になったり、巨大な水柱を作ったり、夕食まで噴水の水とたわむれることになっていた。夕食はライブのバンド演奏を聞きながらの、オリーブ油とガーリックのイタリアン料理であった。
午後はローマの東30km余り行ったヴィラ・デステを見た。ローマを囲む丘の上に、400年前に建てられたルネッサンス時代の別荘である。元はベネディクト派の修道院だったものを枢機卿イッポリト・デステが豪華な別荘に造営した。ここには「100の噴水」、「オルガン噴水」など数百もの噴水が作られていて、様々な工夫がこらされている。隠し噴水から突如として水が飛び出し、庭を散策する人をずぶぬれにさせたり、噴水があつまって滝になったり、巨大な水柱を作ったり、夕食まで噴水の水とたわむれることになっていた。夕食はライブのバンド演奏を聞きながらの、オリーブ油とガーリックのイタリアン料理であった。ナポリ・ポンペイ・ソレント・カプリ
18日目、ローマからナポリを経てソレント地方へ移動する。イタリアはローマの南あたりで東西に線が引かれ、南北で際立った対照を見せる。外国の支配という歴史的背景だけでなく、北の工業、南の農業、その副産物としての貧富の差、それらの結果としての生活文化など。言葉も違うそうである。私の知っているイタリア民謡は「海に来れ」(ヴェネチア)を除いて、すべてが南の地域のものである。
ナポリはローマに次いで古い都市で、元は紀元前7世紀に建設されたギリシャの植民都市であった。ネオポリス(ニュー・シティ)がナポリに訛った。その後この地はフランスやスペインの支配を受けており、ローマとは違った異国情緒を感じさせる。ナポリの町は戦災がひどく古い建物は少ない。民謡に出てくるサンタ・ルチアはナポリからはずれた海岸道路の総称で、小さなサンタルチア港がある。ナポリはカメオの本場で工場の1つを見学した。淡い青やピンク色のカメオに、職人が細かな刃で刻んでいく。土産に大きめのカメオを買った。

 ナポリからバスで40分ほど南に行った所にポンペイの遺跡がある。西暦79年にヴェスヴィアス火山の噴火によってポンペイの町は一瞬のうちに6mもの灰の下に埋もれてしまった。17世紀にはじまった発掘遺跡は町全体におよび、そこには町のインフラがそろっていた。神殿、市場、浴場、劇場、邸宅、中庭、轍の残る石街路、染物屋、洗濯屋、そして売春宿。売春宿では、ダイアンやキャシーなどがかわるがわるベッドがわりの石台に横たわって、写真を撮り合った。若い女の子のはしゃぎかたは罪がない。散策していていると思わぬところにモザイクやフレスコ画にでくわすことがあって、宝捜しをしているみたいで楽しい。フレスコ画はポンペイ朱と呼ばれる独特の赤と黒で、骨董品の壷と同じ深い趣があった。
ナポリからバスで40分ほど南に行った所にポンペイの遺跡がある。西暦79年にヴェスヴィアス火山の噴火によってポンペイの町は一瞬のうちに6mもの灰の下に埋もれてしまった。17世紀にはじまった発掘遺跡は町全体におよび、そこには町のインフラがそろっていた。神殿、市場、浴場、劇場、邸宅、中庭、轍の残る石街路、染物屋、洗濯屋、そして売春宿。売春宿では、ダイアンやキャシーなどがかわるがわるベッドがわりの石台に横たわって、写真を撮り合った。若い女の子のはしゃぎかたは罪がない。散策していていると思わぬところにモザイクやフレスコ画にでくわすことがあって、宝捜しをしているみたいで楽しい。フレスコ画はポンペイ朱と呼ばれる独特の赤と黒で、骨董品の壷と同じ深い趣があった。夕方ソレントに着く。ソレント半島の先端近く、崖の上にある町でオリーブや蜜柑の緑が豊かな保養地である。夕食までホテルのプールで過ごし、食後はタム・タムというナイト・クラブへ繰り出す。入場料2200リラ(約900円)は自己負担。タンバリンを手にフォクダンスや歌で楽しむ健全なクラブであった。
 19日目はカプリ島まで1時間半のクルーズである。国際的なリゾート、カプリ島は古代ローマ皇帝が好んで別荘を建てた地で、美しい海岸線にエメラルド・グリーンの海が延びる。マリナ・グランデから小さなボートで島の西側にある有名な青の洞窟(Blue Grotto)を訪れる。銀を溶かしたような海の下から光が射して、そこだけが明るく青い。島の中央に589mのモンテ・ソラーロがあり、そこから見下ろす地中海とナポリ湾の景色は絶景である。アナカプリからモンテ・ソラーロへ運ぶケーブルが歌にもあるフニコラレである。
19日目はカプリ島まで1時間半のクルーズである。国際的なリゾート、カプリ島は古代ローマ皇帝が好んで別荘を建てた地で、美しい海岸線にエメラルド・グリーンの海が延びる。マリナ・グランデから小さなボートで島の西側にある有名な青の洞窟(Blue Grotto)を訪れる。銀を溶かしたような海の下から光が射して、そこだけが明るく青い。島の中央に589mのモンテ・ソラーロがあり、そこから見下ろす地中海とナポリ湾の景色は絶景である。アナカプリからモンテ・ソラーロへ運ぶケーブルが歌にもあるフニコラレである。 20日目はイタリア南部を横切って、港町ブリンディシに移動する。丘とオリーヴの木が続く南の風景は貧しい。ここからギリシャにむけて1泊の船旅に出るのである。ヨーロッパの旅もほぼ半ば近くを消化した。デッキのプールサイドで焼け付くような地中海の太陽を浴び、ビールを片手に本を読む。完全なリラクゼイションの1日が用意されていた。
20日目はイタリア南部を横切って、港町ブリンディシに移動する。丘とオリーヴの木が続く南の風景は貧しい。ここからギリシャにむけて1泊の船旅に出るのである。ヨーロッパの旅もほぼ半ば近くを消化した。デッキのプールサイドで焼け付くような地中海の太陽を浴び、ビールを片手に本を読む。完全なリラクゼイションの1日が用意されていた。トップへ
6.ギリシャ
| 赤茶色の岩、岩山、やぎ、ろば 黒衣の老婦、刺繍、畑で昼寝する農夫 ターキッシュ・コフィー、オリーブ、ブズーキ Friendly、日本びいき 小柄、浅黒の男性 路端の十字架箱‐交通事故死者の写真 |
メモ書きはイタリアと同じくらいに充実している。フレンドリーとあるのは、国民性としての印象のうえに、親日感のつよいことをさしてのことである。
ここまでイギリス、フランス、ドイツ、スイス、イタリアと見てきたが、ここに来て国の様相が一変したことに気づく。まず緑がすくない。地中海性気候というより、砂漠気候といったほうが実感に近い。家は遠くから見ると純白の漆喰のマッチ箱が並んでいるように見える。
 同じキリスト教でもギリシャ正教のいわゆるビザンチン文化は西ヨーロッパからみれば異質な外国文化に見えたであろう。15世紀から4世紀ものあいだトルコの支配下にあったことも致命傷となった。人の衣装も地味で体格も貧弱である。国の豊かさの尺度に先進性とか民度という言葉があるが、その尺度でいえばギリシァとそれまでみてきた国との間には一線が引かれているように思える。2500年前は世界でトップの超先進国であっただけに、今の姿に歴史の無常を感じざるをえない。アメリカという国がまだ存在せず、日本ではようやく稲作を始めたころに、ギリシャでは選挙とか哲学などが流行していたのであった。
同じキリスト教でもギリシャ正教のいわゆるビザンチン文化は西ヨーロッパからみれば異質な外国文化に見えたであろう。15世紀から4世紀ものあいだトルコの支配下にあったことも致命傷となった。人の衣装も地味で体格も貧弱である。国の豊かさの尺度に先進性とか民度という言葉があるが、その尺度でいえばギリシァとそれまでみてきた国との間には一線が引かれているように思える。2500年前は世界でトップの超先進国であっただけに、今の姿に歴史の無常を感じざるをえない。アメリカという国がまだ存在せず、日本ではようやく稲作を始めたころに、ギリシャでは選挙とか哲学などが流行していたのであった。デルフィ
 22日目、ギリシャ探訪は古代ギリシャの聖地であるデルフィから始まった。コリント湾の北側に、湾を見下ろすように立つパルナッソスの山(570m)の麓にある。悩みを持つ人々はここに来て、アポロンの神殿に詣でてその神託を受けた。個人の悩みも、隣人とのいさかいも、ペルシャとの戦争の戦略も、みんな巫女の告げる意味深長なアポロンの神託に従った。巫女には老女が多かったこと、神がかりになって他人の言葉を発することなど、恐山のイタコの口寄せと似たようなものだった。それに国家運命をかけるというのだから考えるだけで恐ろしい。しかし結果的にはサラミスの海戦でペルシャ軍を撃退する大成功をおさめたのである。
22日目、ギリシャ探訪は古代ギリシャの聖地であるデルフィから始まった。コリント湾の北側に、湾を見下ろすように立つパルナッソスの山(570m)の麓にある。悩みを持つ人々はここに来て、アポロンの神殿に詣でてその神託を受けた。個人の悩みも、隣人とのいさかいも、ペルシャとの戦争の戦略も、みんな巫女の告げる意味深長なアポロンの神託に従った。巫女には老女が多かったこと、神がかりになって他人の言葉を発することなど、恐山のイタコの口寄せと似たようなものだった。それに国家運命をかけるというのだから考えるだけで恐ろしい。しかし結果的にはサラミスの海戦でペルシャ軍を撃退する大成功をおさめたのである。 今アポロンの神殿の場所には輪切りにされた石円柱が積み上げられているのみである。劇場や競技場跡もあり、聖地としての自治都市国家を形成していた。焼け付くような夏の地中海の陽射しをあびて、オリーブの香りの中でこの一画だけが、隔離された別世界を再現している。古代の文明社会の聖地がそっとかくまわれていた。
今アポロンの神殿の場所には輪切りにされた石円柱が積み上げられているのみである。劇場や競技場跡もあり、聖地としての自治都市国家を形成していた。焼け付くような夏の地中海の陽射しをあびて、オリーブの香りの中でこの一画だけが、隔離された別世界を再現している。古代の文明社会の聖地がそっとかくまわれていた。『古代の不思議』の著者、レオナード・コットレルは、自らが選んだ世界7不思議の1つにデルフィのアポロン神殿をあげている。イギリスのストーンヘンジ、ローマのコロセウムについで私が見た3番目の世界7不思議である。
アテネ
 デルフィからアテネに着いた時はもう夜になっていた。アクロポリスの丘の西、演壇の丘と呼ばれる小さな丘に一見劇場風の半円形石段の遺跡がある。直接民主制の頃、アテネの市民はここに集まって雄弁家の演説を聞いていたのである。この場所で毎晩、「音と光り」のパフォーマンスが行われる。ロワール渓谷のシュヌーソ城でみた光と音のスペクタクルと同じ趣向であった。今「音と光り」のプログラムを見ているとフランスのフィリップ・カンパニーとの共同製作とある。シュヌーソの夜を演出した同じ会社であった。ドラマの内容はペルシャ戦争を扱ったものである。パンテオンがライトアップされ、丘の上に幻想的に浮かびあがる。
デルフィからアテネに着いた時はもう夜になっていた。アクロポリスの丘の西、演壇の丘と呼ばれる小さな丘に一見劇場風の半円形石段の遺跡がある。直接民主制の頃、アテネの市民はここに集まって雄弁家の演説を聞いていたのである。この場所で毎晩、「音と光り」のパフォーマンスが行われる。ロワール渓谷のシュヌーソ城でみた光と音のスペクタクルと同じ趣向であった。今「音と光り」のプログラムを見ているとフランスのフィリップ・カンパニーとの共同製作とある。シュヌーソの夜を演出した同じ会社であった。ドラマの内容はペルシャ戦争を扱ったものである。パンテオンがライトアップされ、丘の上に幻想的に浮かびあがる。 この夜のホテルでの夕食では、全員が頭にオリーブの枝冠を飾り、綿地の布1枚を古代ギリシャ風に着て席に着くことになっていた。インド人の着るサリーに似ている。長い1枚ものを着るには6尺ふんどしを締めるような要領がいって、ホテルの従業員が1人1人に着付けして回った。女の子はここでもキャーキャー騒いで楽しそうであった。Tシャツ、短パン姿の女子大生が片方の肩をはだけて白一色のロングドレスに変身すると、それだけでおしとやかになるのはおもしろい。
この夜のホテルでの夕食では、全員が頭にオリーブの枝冠を飾り、綿地の布1枚を古代ギリシャ風に着て席に着くことになっていた。インド人の着るサリーに似ている。長い1枚ものを着るには6尺ふんどしを締めるような要領がいって、ホテルの従業員が1人1人に着付けして回った。女の子はここでもキャーキャー騒いで楽しそうであった。Tシャツ、短パン姿の女子大生が片方の肩をはだけて白一色のロングドレスに変身すると、それだけでおしとやかになるのはおもしろい。翌23日目は朝からアテネ観光である。アテネは人口200万の大都市で国民の5分の1がこの都会に集まっていることになる。プラカという繁華街を歩いていると膝上30センチの超ミニスカートをはいた街娼に声をかけられた。妻がそばにいようと相手はかまっていない。「フレンドリー、日本びいき」とメモに記したのはまさかこの時の印象ではないと思うが。
アテネは古代民主主義と西洋哲学の揺籃の地である。ソクラテス、プラトン、ペリクレスらがかって同じ土の上を歩いていたと思うと楽しい気分にさせられる。ソクラテスは難しい質問を問いかけては「君、なにもわかっていないじゃないか」と、人を困らせていた。そのくせ家に帰ると妻のクサンティッペに怒られてばかりいたのであった。
 アクロポリスに登ってみると採石場かと思うほどに、方形の大理石が無造作に散らばっている。それぞれ意味があってその場に置かれているのか、それとも単に置き場に困って無作為に置かれているのか分からない。日本だったらこれほどの貴重な遺跡物であればもうすこしきちんと整理するだろうにと、散乱している石に同情したくなった。
アクロポリスに登ってみると採石場かと思うほどに、方形の大理石が無造作に散らばっている。それぞれ意味があってその場に置かれているのか、それとも単に置き場に困って無作為に置かれているのか分からない。日本だったらこれほどの貴重な遺跡物であればもうすこしきちんと整理するだろうにと、散乱している石に同情したくなった。丘の頂上にある幅30m、長さ68mの均整のとれたドリア式大理石建造物が女神アテナの神殿である。パンテオンとはギリシャ語で処女という意味だそうである。しかしそのパンテオンは痛いたしかった。屋根は吹き飛ばされ、上部にあるべきフリーズはのっぺらぼうで顔の皮膚をはがされている。大英博物館へ連れ去られたのだ。もって帰れば完璧な整形手術ができるものを。
 パンテオンの北に、ポセイドンを奉ったというエレクテウム神殿がある。6人の乙女の人柱に支えられたポーチが美しいが、1人を除いてみんな顔の表情が無くなっていた。最もよく保存された西から2番目の少女の柱は実は複製で、オリジナルは大英博物館にあるという。
パンテオンの北に、ポセイドンを奉ったというエレクテウム神殿がある。6人の乙女の人柱に支えられたポーチが美しいが、1人を除いてみんな顔の表情が無くなっていた。最もよく保存された西から2番目の少女の柱は実は複製で、オリジナルは大英博物館にあるという。アテネから西に10kmのところに古代アテネ以来の港町ピレウスがある。ギリシャの海の玄関であり、富豪のヨットの溜まり場であり、映画「日曜はダメよ」の舞台になったところでもある。この映画の主人公がメリナ・メルクーリで、カンヌ映画祭の主演女優賞を受賞した。ギリシャが生んだ唯一といってよい国際女優である。
彼女が政界に入って文化相になったとき、外国にあるギリシャ文化財の返還運動を起こした。彼女の頭の中にはミロのヴィーナスの他にも、おそらくパンテオンのフリーズや美しい乙女の石柱もあったことであろう。戦争という暴力は文化財にもおよぶ。宝物を独占したいという、女が宝石を集めたがる欲望の本質はなんであろうか。
 夜はプラカのレストランで、マンドリンに似たギリシャの楽器ブズーキ演奏を聞きながら夕食をとった。食事は過剰なオリーブ油ときつい香料のせいで、喉に通らなかった。シシカバブも好きになれない。土産にお決まりの、人形とミュージック・テープを買った。ギリシャの人形は黒いスカートに円錐形の長いぼうしをかぶり、飛び出すような胸だけが立派な、個性的な女性であった。ぶりっ子ぶったところがない、純朴で粗野なところが気に入っている。
夜はプラカのレストランで、マンドリンに似たギリシャの楽器ブズーキ演奏を聞きながら夕食をとった。食事は過剰なオリーブ油ときつい香料のせいで、喉に通らなかった。シシカバブも好きになれない。土産にお決まりの、人形とミュージック・テープを買った。ギリシャの人形は黒いスカートに円錐形の長いぼうしをかぶり、飛び出すような胸だけが立派な、個性的な女性であった。ぶりっ子ぶったところがない、純朴で粗野なところが気に入っている。イドラ島
 24日目は、ピレウスから3時間の船旅で、エーゲ海に浮かぶ小島に渡る。壁を漆喰で塗りたくった真っ白な家が島を覆っている。18世紀に東地中海の海上貿易を独占し巨万の富を築いた船主たちの大邸宅がある。またこの島には多くの芸術家が住んでいて、芸術家の島とも呼ばれる。そんな小島でなんとなくドンキーの背中に跨いでせまい道や石段を上り下りしてみたり、夜は満天の星を仰いで屋上テラスで雑魚寝をして、子供心に帰ろうという趣向である。夜の食事は島の漁師たちと一緒で、食後シルタキというワイルドなギリシャ・フォークダンスを教えてくれた。私も妻も参加して、早いテンポで踊りまわるものである。
24日目は、ピレウスから3時間の船旅で、エーゲ海に浮かぶ小島に渡る。壁を漆喰で塗りたくった真っ白な家が島を覆っている。18世紀に東地中海の海上貿易を独占し巨万の富を築いた船主たちの大邸宅がある。またこの島には多くの芸術家が住んでいて、芸術家の島とも呼ばれる。そんな小島でなんとなくドンキーの背中に跨いでせまい道や石段を上り下りしてみたり、夜は満天の星を仰いで屋上テラスで雑魚寝をして、子供心に帰ろうという趣向である。夜の食事は島の漁師たちと一緒で、食後シルタキというワイルドなギリシャ・フォークダンスを教えてくれた。私も妻も参加して、早いテンポで踊りまわるものである。夜は民家の屋上をかりて、ラグ1枚を敷いた上で天を仰いでの雑魚寝であった。皆が寝静まった頃にミシシッピーの独身カップルから意味深長な声がもれてくる。息使いがあらくなってきて、必死に押し殺した女のうめくような声も聞こえる。――なにも、ここで…――と思いつつ、空を見ながらなかなか寝付けなかった。地中海性気候はあくまで健康的である。
 翌日は1日中自由行動で、島の繁華街でショッピングを楽しむことにした。貝殻や、黄色のばかでかいスポンジのような海綿が店に並んでいるのは、いかにも小島の銀座らしい。一方で意外にも宝石を売る店が多かったことには訳がある。その昔この島の沖合いに、古代の秘宝のイルカに乗った少年の黄金像が沈められた。ある日、はちきれんばかりの肉体をもった、海綿とりの海女が海底でその秘宝を見つけたのである。
翌日は1日中自由行動で、島の繁華街でショッピングを楽しむことにした。貝殻や、黄色のばかでかいスポンジのような海綿が店に並んでいるのは、いかにも小島の銀座らしい。一方で意外にも宝石を売る店が多かったことには訳がある。その昔この島の沖合いに、古代の秘宝のイルカに乗った少年の黄金像が沈められた。ある日、はちきれんばかりの肉体をもった、海綿とりの海女が海底でその秘宝を見つけたのである。ソフィア・ローレンがアメリカに渡って初めての主演映画が「島の女」、英語題名は「イルカに乗った少年」であった。
 その島の店にはイルカの指輪が多かった。私はドルフィンが好きである。おでこが大きくて賢そうで、瞳がつぶらでかわいくて、人なっつこくて、いたずら好きで、ペットのような感じがする。2500ドラクマするドルフィンの指輪を買った。おまけにダイヤと金とルビーの、盛りだくさんの指輪も買ってしまった。こちらは7200ドラクマだから7万2000円ということになる。意外なところで意外な買い物をして、今後の予算が大幅に狂ってしまった。ニューヨークからセントルイスへ帰る飛行機賃がなくなったのだ。バスで帰るしかない。
その島の店にはイルカの指輪が多かった。私はドルフィンが好きである。おでこが大きくて賢そうで、瞳がつぶらでかわいくて、人なっつこくて、いたずら好きで、ペットのような感じがする。2500ドラクマするドルフィンの指輪を買った。おまけにダイヤと金とルビーの、盛りだくさんの指輪も買ってしまった。こちらは7200ドラクマだから7万2000円ということになる。意外なところで意外な買い物をして、今後の予算が大幅に狂ってしまった。ニューヨークからセントルイスへ帰る飛行機賃がなくなったのだ。バスで帰るしかない。テッサロニキ
26日目、小島生活を満喫して再び大陸にもどる。車は一路マケドニアのテッサロニキに向う。テッサロニキはアレクサンダー大王の妹の名である。紀元前315年、彼女と結婚していたマケドニア総督カサンデルによってつくられた都市で、のち305年ローマ皇帝ガレリウスの時代には東ローマ帝国の首都にもなった。町のメインストリートには今も堂々としたガレリウス凱旋門が立ちはだかっている。
海岸近くに象の脚のような巨大な円塔が立っている。もとは要塞であったがスルタン・マムードのときここで虐殺が行われ、それ以来「血の塔」と呼ばれるようになった。トルコ政府はマイナスイメージを拭い去るために塔全体を白く塗りつぶした。それ以来この塔は「白い塔」とよばれ、テッサロニキのシンボルとなっている。ただ大きなレンガの固まりがあるだけで、なんの美的香りもない。
アテネからここまで、北に上がるにつれ国土が豊かになっていくのに気がつく。石灰岩の岩山と乾いた土から、緑と水の景色が増えて来て、畑にはドンキーにかわってトラクターの姿にであう。風土というものはおもしろい。
北に少し行くだけで、社会主義国のユーゴスラビアに入る。
| トップへ 続きへ |